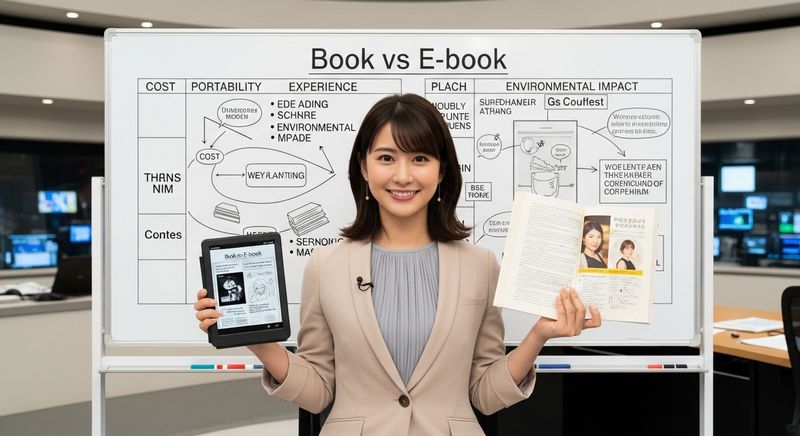
電子書籍派がトレンドになっているらしい「読書の日」
10月27日は「読書の日」だそうです。1947年に出版社などが出版界の振興を目的として制定したもので、毎年10月27日から11月9日までの約2週間を「読書週間」とし、その初日が「読書の日」と定められています。今日はXに、ハッシュタグで「#電子書籍派」というポストが目立ちました。
ネットの時代、読書も急速に急速に電子書籍の普及が進んでいるようです。
私も、書籍の場所のコストや、検索等の便利さを考え、電子書籍で購入・閲覧する機会が増えてきました。
一方で、従来の紙の本の良さを愛する方も依然として多くいらっしゃいます。
紙の書籍の魅力、それは「物」としての存在感
あなたは #本派 #電子書籍派 ? 私は本派。1??読んだものが残り、本棚を見てこんなに読んだという感動がある。本棚の本にその時の思い出が付属する。2??パラパラとめくり前の文を簡単に探せる。パラパラとめくり全体の内容が、簡単にわかる3??本を読んでる実感がある4??本の大きさ、文字を見て 1/2 pic.twitter.com/yWzQvWuIwk
— I??かがわ (@EOqJzTYKkGomS97) March 6, 2024
テレビやユーチューブ動画で、学者や評論家などが、本棚をバックに写っているシーンがあると、「知識人はさすがに本をたくさん読むんだな」というふうに感じた方もおられるのではないでしょうか。
本の所持は、その存在が、知識があるかのようなステータスになっている面があります。
多くの研究で、紙の本の方が内容の記憶定着率が高いという報告を聞きます。
ページのどの辺りにどんな内容が書いてあったかという「場所の記憶」が手がかりとなり、記憶を呼び起こしやすくしてくれるのです。
電子書籍だと、すぐに検索できるので、「場所の記憶」は必要ないため、その能力は使われないんだと思います。
それに、電子書籍は便利なようでいて、意外と不便です。
電源がないと見られませんから、紙の本のように、かばんにつっこんで、どこで、どんな場面で、どんな姿勢で読むかが不問、というわけにはすかないですよね。
あとは、自分の感覚として、やはり電子書籍のほうが目がつかれます。
今は、紙の本も質が良くなり、光沢紙が部屋の電光でまぶしいと感じることがありますが、それでも疲労感は電子書籍のほうがあります。
電子書籍の利点、それは「機能」としての便利さ
一方、SNSで「派」が増えている、電子書籍の利点ですが、スマートフォンやタブレット一台に、何百、何千冊もの本を収納できるのがいいですね。
持ち歩きの便利さ
紙の本を何冊も持ち歩くのは、文庫本でも大変です。
通勤・通学中や旅行時の荷物を大幅に軽減してくれます。まさに「持ち運べる図書館」です。
それは、保存・管理の便利さにもつながっています。
保管はゼロスペース
紙の書籍は、その書籍の代金だけでなく、場所のコストもかかります。
一般の個人ではそういないかもしれませんが、本が溜まれば、書庫としての部屋が必要です。
そのために、アパートを借りている人だっています。
それが、電子書籍なら、ゼロスペースです。
すべて、クラウドにしまって置けるのです。
これは、本が増えれば増えるほど、ありがたみが分かります。
検索やコピペの便利さ
前述のように、すぐに検索できるので、「場所の記憶」は必要ありません。
記憶力の良し悪しに関係なく、その書籍を有効利用できるのです。
書籍の引用をする場合、コピペが使えます。
長文になると、一字一句間違えないように引用するのは結構神経使うのです。
すぐに入手できる
電子書籍は、インターネット環境さえあれば、深夜でも休日でも、欲しい本をその瞬間に購入して、すぐに読み始められます。
私は気が短いので、すぐに読めないと情熱が失せてしまうのです。
この「即時性」は、書店が閉まっている時間帯や、遠方に住んでいる方にとっては特に大きなメリットです。
そして、書籍は、再販制度(再販売価格維持制度)によって定価販売が義務付けられており、割引をしてはいけません。
しかし、電子書籍ですと、販売元が採用しているポイントで減額できます。
電子書籍ってなんだ
#おはようございます!#紙の本派?#電子書籍派?
『電子書籍のメリット』
①持ち運びが楽
②本の保管が簡単
③紙の本より安価
④購入した直後から読める
⑤読み返したいときすぐ探せる
⑥ハイライト機能で復習が楽
⑦満員電車でも片手で読める
⑧老眼に優しい#読んだら忘れない読書術#樺沢紫苑— 尾崎コスモス/読んで書く人 (@ozaki_cosmos) May 22, 2022
「ところで、その電子書籍ってなんだ?」と思われる方も、もしかしたらおられるかもしれませんね。
簡単に述べれば、デジタル形式で作成された書籍です。
いくつかの形式がありますが、大きく分けると2種類になります。
EPUB形式
これは世界標準の規格です。
たとえば、Amazonで売っているKindleという電子書籍のブランドは、このEPUB形式をもとに、AZW, KFXなどといった独自規格を加えて販売しています。
ライブドアブログでは、ブログをEPUB形式に変換できる機能が標準で用意されています。
つまり、ライブドアブログのユーザーは、ご自身のブログを、Kindleとして販売できるということです。
PDF形式
これは、一般の人たちも、仕事その他の文書データのやりとりに使われている形式です。
紙のページをそのままデジタル化し、レイアウトが固定されているため、図版や写真が多い雑誌、美術書、マンガ、学術書などに向いています。
また、Windowsであろうが、Macであろうが、Linuxであろうが、ハードに依存しない形式なので、デバイスを持っていれば、データのやり取りが確実に行える点が便利です。
断捨離で、手持ちの紙の書籍をデジタル化した場合、このPDF形式で保存することが多いですね。
二者択一ではなく、使い分けの時代
【開催中!】三省堂書店×BookLive!「あなたはどっち派? 紙本vs電子書籍 総選挙!」電子書籍プリペイドカード1万円分が当たったら、何を買おう…(*´∀`*)#電子書籍派 なら積ん読してもかさばらない!#紙vs電子総選挙 ⇒https://t.co/BsSz442ApQ pic.twitter.com/eTSnRK3ynP
— ブックライブ (@BookLive_PR) October 26, 2017
まあ結論としては、どちらも必要だと思いますので、目的に応じて使い分けていくということでいいのではないかと思います。
私も、前述のように目がつかれるので、すべてを電子化するのもどうかなあと思い、時々紙の書籍にしています。
でも、スマホやタブレットの時代に、若い人が「#電子書籍派」というハッシュタグは、それらのデバイスで読書をしているということの証ですから、それはそれで何よりと思います。
漫画が多いみたいですけどね。漫画だって読書のうちです。
みなさんは、電子書籍は利用されていますか。

文春文庫電子書籍ベスト100【文春e-Books】 – 文藝春秋


コメント