
2025年、日本各地でクマによる被害が過去最悪のレベルに達しています。環境省の発表によると、今年度上半期だけでクマの出没件数は約2万件を超え、前年度の1年分を上回る異常事態となりました。
さらに深刻なのは人的被害で、死亡者数は12人に達し、これまで過去最多だった2023年度の6人から2倍に増加しています。
捕獲数も急増しており、今年度上半期だけで6,063頭が捕獲され、2006年度以降で最多を記録しました。「異常出没」とされた2023年度のペースをも上回るこの状況に、政府は関係閣僚会議を開催し、人里に侵入したクマの迅速な駆除に向けた緊急対策を進めています。
なぜこれほどクマが出没するのか
クマ被害が各地で相次いでいます。被害の状況やクマ対策についてはNHK ONE ニュースでまとめてご覧いただけます↓https://t.co/jk0Q1Q9r4y
詳しい情報はNHK ONE ニュース・防災アプリでも↓https://t.co/lveHsAAnqF pic.twitter.com/ignQOkUhc8
— NHKニュース (@nhk_news) November 7, 2025
専門家によると、クマの異常出没にはいくつかの要因が重なっています。ドングリなどの堅果類の不作により、山中での餌が不足していることが大きな理由の一つです。さらに、個体数の増加や、森林開発により人里との境界が曖昧になったことも指摘されています。
特に問題視されているのが、メガソーラー開発などによる大規模な森林伐採です。これによりクマの生息地が縮小し、餌を求めて人里に降りてくるケースが増えているとされています。また、一度人里で餌を得たクマは、その場所を記憶し何度も訪れる習性があるため、被害が繰り返される傾向にあります。
進む捕殺対策とハンター不足の現実
この緊急事態に対し、政府と自治体は捕殺を中心とした対策を強化しています。警察庁は深刻なハンター不足を補うため、11月13日から秋田県と岩手県で警察官によるライフル銃駆除を開始する方針を決定しました。緊急猟銃を実施できる者の拡大措置も議論されています。
しかし、この捕殺中心の対策は、現場の自治体にも新たな問題をもたらしています。クマを駆除した自治体には「なぜ殺した」「このクマ殺し!」「人間が駆除されるべき」といった抗議の電話やメールが殺到し、対応に苦慮しているのです。
日本熊森協会の主張:「捕殺だけでは解決しない」
「捕殺だけでは解決しない」「子グマ殺すな」日本熊森協会が緊急要請、環境省に対策見直し求める https://t.co/z5jqDwLWJ0
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) November 6, 2025
こうした状況の中、自然保護の観点からクマの保護を訴える日本熊森協会が、環境省に対して緊急要望書を提出しました。協会は「捕殺だけでは解決しない」「子グマ殺すな」という立場から、現在の対策の見直しを求めています。
協会の室谷悠子会長は「過剰な捕殺は抑制しなければならない。人とクマとの間に距離を置くことが大事だ」と訴えています。特に子グマの捕殺については「生命倫理の観点から人道的に問題がある。戦時下でも女性や子供は殺さないのがルール。子グマに手を付けるのは間違っている」と強く批判しています。
協会は捕殺そのものに全面的に反対しているわけではなく、必要な場合もあると認めつつも、「捕殺で数を減らすことに偏った対策から脱却し、人とクマの生活圏をすみ分ける政策と予算化を求める」としています。
この主張をどう見るべきか
熊森協会の主張には一理ある部分もあります。実際、クマは生態系の頂点に立つ重要な生物であり、種子の散布など生態系維持に重要な役割を果たしています。無秩序な大量捕殺が生態系のバランスを崩す可能性は否定できません。
また、専門家も「すべてのクマ事故は防げる」と指摘し、予防対策の重要性を強調しています。緩衝地帯の整備、藪の刈り払い、餌となる生ゴミの適切な管理など、クマを人里に寄せ付けない環境づくりこそが根本的な解決につながるという意見もあります。
しかし一方で、現実に人命が失われている状況で「子グマを殺すな」という主張は、被害者やその家族、危険にさらされている地域住民の立場を軽視しているとの批判もあります。SNS上では「人を襲うならマムシや蜂と同じく殺すべき」「被害者軽視だ」といった反発の声が数多く上がっています。
求められるバランスの取れた対策
この問題に単純な答えはありません。重要なのは、短期的な安全確保と長期的な共存策のバランスを取ることです。
短期的には、人命を守るための緊急的な捕殺もやむを得ない場合があるでしょう。しかし同時に、長期的視点から森林と人里の境界に緩衝地帯を整備し、クマの生息地を保全しながら人間の生活圏との分離を図る必要があります。
また、北海道や島根、兵庫、長野などの一部地域では、野生動物の知識と管理技能を持った専門家を配置し、効果を上げている事例もあります。こうした専門人材の全国的な配置や、電気柵などの物理的な防除策の普及も重要です。
クマ問題は、人間と自然の関係を見つめ直す機会でもあります。駆除か保護かという二項対立ではなく、科学的知見に基づいた総合的な対策が求められています。それには予算の確保、専門家の育成、住民の理解と協力が不可欠です。私たち一人ひとりが、この問題を自分事として考えていく必要があるのではないでしょうか。


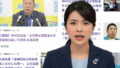
コメント