
NotebookLMという、Googleが提供しているGeminiを用いたAIリサーチアシスタントは使われていますか。PDFや音声、Googleドキュメント、YouTube動画などを読み込み、AIが当該コンテンツの要約や分析を行うツールですが、ブログ記事も作ってくれるのです。
NotebookLMは、PDF化された書籍やサイトのページ、YouTubeのURLを読み込ませることで、その要約、マインドマップ、音声や動画による概略説明、そのデータを元にしたテストやレポートなど様々な分析を行ってくれます。
そのユーザーの情報についてまとめてくれるので大変便利です。
その「レポート」のひとつとして、NotebookLMはブログ記事の作成に非常に役立ちます。
といっても、一般的なAIチャットのように「〇〇についてのブログ記事をゼロから書いて」と指示するのとは、少し得意分野が異なります。
NotebookLMは、提供した情報源(ソース)に基づいて文章を生成したり、アイデアをまとめたりするのが得意なツールです。
NotebookLMを使ったブログ記事作成の具体的な活用法
NotebookLMは、「リサーチ・執筆パートナー」として機能します。
情報源(ソース)のアップロード
まず、記事のトピックに関連する資料をNotebookLMにアップロードします。
(例:参考にしたWeb記事、PDFの論文、あなた自身が書いたメモ、Googleドキュメントなど)
記事の「土台」を作らせる
構成案の作成
「アップロードした資料に基づき、[トピック名]についてのブログ記事の構成案を作成してください。」
要約の作成
「これらの資料の重要なポイントを、ブログの導入文として要約して。」
アイデア出し
「これらのソースから、読者の関を引きそうなブログのタイトル案を5つ考えて。」
本文の執筆(草稿)をサポートさせる
セクションごとの執筆
「構成案の『〇〇』の部分について、ソースの[資料A]と[資料B]を使って草稿を書いてください。」
Q&Aで内容を深掘り
資料について質問をすると、NotebookLMがソースに基づいて回答してくれるので、それを記事の本文に活用できます。
NotebookLMを使う最大のメリット
最大のメリットは、AIが不正確な情報や「それらしい嘘」を創作する(ハルシネーション)のを防ぎやすい点です。
NotebookLMは、ユーザーが提供したソースに忠実な回答や文章を生成するように設計されています。
そのため、専門的な内容や正確性が求められる解説記事などを書く際に、非常に強力なアシスタントとなります。
いうまでもないかもしれませんが、書籍のレビューは、NotebookLMの得意分野と非常に相性が良いです。
なぜなら、レビューの「情報源(ソース)」が「その書籍」という明確な1冊(あるいは、ユーザーの読書メモ)に定まるからです。
なぜ書籍レビューに適しているか
1.記憶違いや「不正確な引用」を防げる
・レビューを書く際、「あの登場人物、何て言ってたっかな?」「著者の主張は正確にはどうだったか?」と曖-昧-になることがあります。
・NotebookLMに書籍のテキスト(PDFやスキャンデータ)や、ご自身の詳細なメモをソースとして読み込ませれば、正確な記述や引用に基づいたレビューが書けます。
2.自分の「感想」と「本文」を結びつけられる
・ユーザーが書いた「読書メモ(感想)」もソースとしてアップロードできます。
・「(ソース内の)私のメモで『感動した』と書かれている部分と、それに関連する書籍の本文(ソース)を抜き出して」といった指示が可能です。
3.深い分析や構成案の作成が容易になる
・書籍全体をソースとして、「この本の中心的なテーマは何か」「著者が最も伝えたかったことは何か」を要約させることができます。
・それを元に、「このテーマに基づいたレビュー記事の構成案を作って」と指示すれば、説得力のある記事の骨組みが完成します。
活用ステップの例
ソース準備
レビューしたい書籍のデータ(PDFなど)と、ご自身で書いた読書メモ(Googleドキュメントやテキストファイル)を用意します。
アップロード
それらのファイルをNotebookLMにアップロードします。
アイデア出し
「(書籍とメモのソースに基づき)この本の魅力を伝えるキャッチーなレビュータイトルを5個考えて」
構成案作成
「この本を紹介するレビュー記事の構成案を作って。特に私のメモにある『〇〇(例:物語の後半の展開)』の部分を厚めに書いて」
執筆サポート: 「構成案の『あらすじ』部分を、ネタバレしすぎないように要約して」「『最も印象に残った点』について、私のメモと本文の引用を使いながら草稿を書いて」
このように、NotebookLMを「優秀な読書パートナー兼編集者」として使うことで、ご自身の感想をより深く、正確に反映させた質の高いレビュー記事を作成できます。
簡単に言えば、「全自動で書いてもらう」のではなく、「自分の資料や知識を、AIと一緒に整理・再構築して、質の高い記事に仕上げる」ためのツールです。
これによって、レビュー記事の作成は、ぐんとグレードアップできますね。

できるGoogle NotebookLM 可能性は無限大!自分専用AIノート活用法 できるシリーズ – 清水理史, できるシリーズ編集部
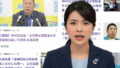

コメント