
つつが虫病は、リケッチアという細菌によるダニ媒介性の感染症で、2025年には10年で最多となる患者数が確認され話題になっています。本記事では、その概要、増加の背景、全国レベルでのリスク、患者数の推移、具体的な対策について詳しくご紹介します。
つつが虫病(Orientia tsutsugamushi)について、AIのPerplexityにまとめてもらいました。
つつが虫病は、主にダニの一種である「ツツガムシ」の幼虫に刺されることで感染します。
日本では、北海道と沖縄を除く多くの地域で発生し、特に野山や草むらなどツツガムシが生息するエリアで感染リスクが高まります。
要するに、農作業者のリスクが高い病気ですが、ヒトからヒトへの感染はありません。
症状は、発熱・発疹・倦怠感が典型で、刺し口(黒いかさぶた)がみられることもあります。抗菌薬(テトラサイクリン系など)により治療が可能ですが、初期対応が遅れると重症化や死に至ることもあります。
2年前には青森、昨年は沖縄などで死亡が報告されました。
つつが虫病が増えている理由
今日の情報源です。
60代女性がつつが虫病 今年確認された患者は10年で最多の11人に|ABS NEWS NNN https://t.co/bkiY4ywJ5m
— 赤べコム (@akabecom) November 15, 2025
近年患者が増加しつつある背景には、以下の要因が挙げられています。
・高齢者の野外活動や農作業が増えていること
・気候変動によるツツガムシの分布拡大や活動期間の変化
・ダニの生息地の拡大と季節ごとの活動範囲の増加
・感染症に対する知識不足、予防対策の徹底不足
他にも、ヒトの移動拡大や行楽需要の高まり(登山・キャンプ等)も一因と考えられています。
全国レベルでのリスク
青森県は26日、青森市の80代女性がつつが虫病にかかり、13日に市内の医療機関で死亡したと発表。県内のつつが虫病による死亡は今年初めて。県保健衛生課によると、女性は今月上旬に発熱や発疹などの症状が出て、8日に医療機関に入院していた。 pic.twitter.com/UHfYuGM23T
— 暗号1955 (@kVAZ2ACQ1dnrPXy) June 26, 2023
かつて東北地方の一部や中部地方の風土病とされていましたが、現在は新潟県を含む本州各地、九州や四国など広範囲で発生が確認されています。
新潟では春から初夏、東日本では秋季、西日本では春秋の二峰性で患者が報告されています。
ツツガムシにはいくつか種類(型)があり、それぞれ活動する時期や分布が異なりますが、全国的に注意が必要な疾患となっています。(https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/tsutsuga/index.html)
近年の患者数の推移
つつが虫病の全国報告患者数は、戦後の衛生環境の改善で一時減少したものの、1984年に957人の最多記録を出して以降増減を繰り返してきました。
2000年以降は年間300?500人で推移しており、最近では高齢者を中心に再度増えつつある傾向にあります。2025年には一部地域で10年ぶりの高水準となったことが報道されています。(https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/Scrub-Typhus/010/tsutsugamushi.html)
ツツガムシにはいくつか種類(型)があり、それぞれ活動する時期や分布が異なりますが、全国的に注意が必要な疾患となっています。(https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/Scrub-Typhus/010/tsutsugamushi.html)
例年、60代以上の高齢者が半数以上を占め、男女比ではやや男性多めですが女性も多い状態です。年齢中央値は男性68歳、女性71歳と高齢層に多発しているのが特徴です。(https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/tsutsugamushi-m/tsutsugamushi-iasrtpc/11415-510t.html)
高齢者は、免疫力や体力が低下しているため、症状が重くなりやすく、重症化や合併症(肺炎・多臓器障害など)が起きやすいことが特徴です。急激な全身状態の悪化や、持病の悪化もよくみられます。(https://kids-doctor.jp/magazine/2pp09ifuvn)
子どもでは、特徴的な刺し口や発疹が目立たないこともあり、初期の発熱が風邪と見分けにくい場合があるため、発見が遅れることがあります。体力や免疫力の未熟さから高熱や強いぐったり感を呈しやすい点も特徴です。(https://mymc.jp/clinicblog/211939/)
つつが虫病対策
つつが虫病を予防するために重要なポイントは以下の通りです。
・草むらややぶ、河川敷などツツガムシの生息地に入る際は長袖・長ズボン、帽子・手袋などで肌を隠す
・袖口やズボンの裾をしっかり閉じる
・虫よけスプレーを衣服や肌に使う
・野外活動後はすぐ入浴し、皮膚や衣類にダニが付いていないか確認する
・発熱や発疹、刺し口(黒いかさぶた)があれば早期に医療機関を受診する
農業従事者や野外レジャーを楽しむ方は特に注意が必要です。
(https://kobe-kishida-clinic.com/infectious/infectious-disease/tsutsugamushi-disease/)
トからヒトへの感染はありませんが、毎年死亡例も報告されているため油断は禁物です。
マダニが媒介するダニ媒介性脳炎の予防ワクチン「タイコバックR」が、2024年3月に国内で承認され、予防が可能になりました。
しかし、つつが虫病には、2025年現在、日本で利用可能な予防接種はありません。
そのため、予防は主に環境対策や個人防護に限られています。
抗生物質による早期治療は有効ですが、予防投与(感染前後の薬の服用)は、年齢問わず一般的には推奨されていません。
つつが虫病は、早期発見・早期治療が重症化防止につながるそうなので、野外活動後に発熱や発疹、刺し口が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診するに限ります。
まだ、感染するリスクは、一般にはそれほど高くないかもしれませんが、これからはわかりませんので、「自然に恵まれた」ところに行かれる際は、留意された法が良いと思います。
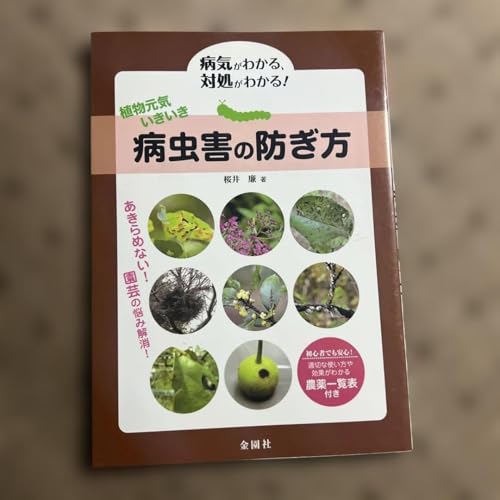
植物元気いきいき病虫害の防ぎ方 病気がわかる 対処がわかる 農薬一覧表


コメント